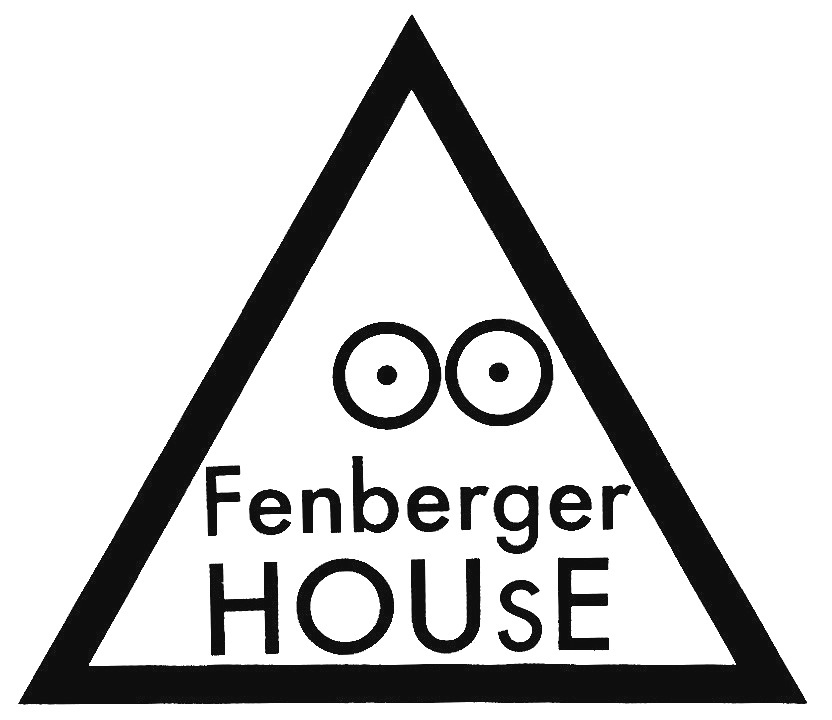クリスタル・ホライズン
/1980年8月、ラインホルト・メスナーは二度目のエベレスト登頂を果たした。単独で成し遂げたのは彼が初めてで、それも無酸素登頂だった。
メスナーは、このときの体験を綴った自著に『The Crystal Horizon』(邦題は『チョモランマ単独行』)という題名をつけた。この「クリスタル・ホライズン」という言葉は、彼の肉体および精神状態のぎりぎりの限界を明示するものであった。
メスナーは、アルプス登山のパイオニアのなかでも、とくにジョージ・マロリーやモーリス・ウィルソンやF.S.スマイスに、強い共感と尊敬の念を抱いている。これらの登山者たちは、基本的に酸素ボンベを使用せず、軽装備・迅速・最小登山期間といった特徴をもつアルパインスタイルに忠実な方法で、山に臨んだ。
メスナーをはじめ、高峰に挑むアルピニストたちの著作を読んで明らかになったことは、ひょっとしたらあまり知られていない登山の一面かもしれなかった:それは多くの登山者の、高地でのさまざまな幻覚の経験である。酸素ボンベを使用しないと低酸素症が起きる。また、登山者は例外なく極度の疲労や睡眠不足や、その他様々なストレス状態に置かれる。それが幻視や幻聴や体感幻覚などを引き起こすのである。世界でも有数の登山家たちの多くが、標高の高さを極める山の頂上で変性意識状態を経験していることに、私は心を奪われた。
その恰好の例がここにある。フランク・スマイスが1933年にエベレストの頂上付近から下山する途中で経験した幻覚について、自ら残した詳しい記述である:
「第6キャンプへ戻る途中、ふと見上げると、青空に黒い物体が二つ浮かんでいた。形は凧式気球に似ていたが、片方には短いずんぐりした羽があるようだった。二つは音もなく漂いながら、まるで息をしているかのように鼓動を打っていた。私は唖然としながらも、強い関心をもって見つめていた。自分の脳は正常に機能していると感じていたが、試しに目を逸らせてみた。二つの物体は私の見つめる先へと動くことはなく、視線を元に戻すとそこにあった。そこでもう一度、目を逸らせ、今度はメンタルテストのつもりで景色の細かな点をつぶさに確認した。それでも、視線を元に戻すとまだそこに見えていたのだ。2、3分後、エベレストの北東の肩を霧が横切り、物体が宙に浮かんでいる上へとかかった。霧が厚くなるにつれその二つは徐々に隠れ、見えなくなった。数分後に霧は晴れた。私はまた見えるのではないかと期待しながら再び見つめたが、現れたときと同様、謎のように消えていたのだ。もしそれが錯覚だったとすれば、とても奇妙なものだった。ただし疲労のせいで、きわめて正常な、理にかなった説明ができなくなっていた可能性はある。このことについて私が言えるのはそれだけで、それ以上は分からないままだ」
高峰登山が人間の心身に及ぼす影響については、僅かながら信頼できる医学文献がある。幻覚という精神の徴候に焦点を絞った論文や書物がいくつかあり、山での多様な経験の概要が述べられている。そこには、声が聞こえる、克明な光景が見える、身体が大きくなったり分離したりするといったものや、俗に「サードマン現象」と言われる、誰かが後ろをついてきたり、そばにいるように感じたりするといったものまでが含まれている。
高峰に臨んだ登山家たちが幻の相棒の存在を報告する例は、枚挙にいとまがない:イェジ・ククチカは誰かほかの人たちのために食事を作っているように感じ、ダグ・スコットは実際より多くの人が山にいるような気がした。エド・ウェブスターは仏教の葬式が行われているのが見え、ジャン・トロワイエは、マーチング・バンドとスキーヤーが見えたり聞こえたりした。そしてラインホルト・メスナーは、料理をしてくれと頼んでくる目に見えない存在を感じたという。
1909年にパブロ・ピカソは『ヌード』という題名のキュービズムの作品を描いた。この絵は現在、日本のポーラ美術館が所蔵している。この作品では、おそらく女神であろうヌードの女性が、背景に見える高い山から現れている。彼女の身体と山の区別はごくわずかで、複雑なキュービズムの手法で画面は切り分けられ、脈打っている。まるで女神の像が一時的に人間の文化領域に降り立ち、なんらかの判読可能な形を装ったかのようである――だがそれは不安定で魅惑的なフォルムを残している。山の遥か上の世界で、彼女は溶けて水や霧や風や氷になるのだろうか。ピカソはここにアーキタイプとしての記憶を描き出しているのだろうか。
高い山々は、神や女神の世界である。こんにちでは、資本のネットワークにすっかり操縦され、晒されている場所でもあるが(サムスンは、2011年に登山家ケントン・クールのスポンサーとなり、エベレストの頂上で携帯電話のギャラクシーS2を使用してもらった)、いっぽうでは人間の心身がさまざまな幻を見て、徐々に死に向かっていくところでもある。高嶺では、現代人の消費者としての身体は少しずつ消失し、夢や、不安定性や転移の世界へと回帰するようである。高い山々は、ひょっとしたら我々の祖先が初めて絵を描いた深い洞窟と、完璧な相似をなしているのかもしれない。ジョルジュ・バタイユの言葉にあるように、そのような場所とは、人間が「死の深い裂け目に宙吊りになっているにもかかわらず、雄々しい力がみなぎっている」のである。
ロジャーマクドナルド、2015年。